試合結果
得点
5'中山克広(清水)
22'西尾隆矢(C大阪)
(ヤンマースタジアム長居、晴、9.2度)
スタメンと配置

清水の攻守の特徴に沿いながらこの試合について考える。
まずは攻撃の局面から。中でも清水の得点を狙う形からみていく。
ここまでの試合、清水のチャンスは左サイドが起点になることが多いと感じる。よく見られるのが下に表した形。

左ワイドにカルリーニョス。広がった相手のSB- CB間のスペースを片山が狙う。ゴール前にチアゴサンタナ。ファーに後藤と中山が入っていく。
ここから狙うは主に以下の3つ。
1)片山にパスを出してポケットからクロス
2)片山に相手の中盤がついたらそのスペースにカルリーニョスがカットインしてシュート。(動画はちょっと違うけど左ワイドで持ったらハーフスペース突撃とそれにより空いたスペースを使うところを見てください。)
🎦 ゴール動画
— Jリーグ (@J_League) 2021年3月6日
🏆 明治安田生命J1リーグ 第2節
🆚 清水vs福岡
🔢 1-0
⌚️ 12分
⚽️ カルリーニョス ジュニオ(清水)#Jリーグ#清水エスパルスvsアビスパ福岡
その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXLYeZ pic.twitter.com/TbJoM3dYL6
3)インスイングのクロスをファーに入れて後藤や中山がゴールを狙う。
/
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2021年2月27日
清水が逆転!
クロスに #後藤優介 が飛び込んだ!
\#DAZNスーパープレー をつけて投稿すると、
DAZN公式がピックアップしてプレー映像を投稿❗
🏆明治安田J1第1節
🆚鹿島×清水
📺#DAZN でライブ中#2021のヒーローになれ #Jリーグ開幕@spulse_official pic.twitter.com/vYEpbFzmvG
ポジションや役割が入れ替わることはあるが、これに近い動きは頻繁に見せる。また上記の形を作るための左サイドへのボールの運び方も相手に合わせて変化する。
開幕から2試合は中村慶太をIHの位置でプレーさせカルリーニョス、片山と三角形を作り崩しながら左サイドを前進していた。
C大阪戦ではここが少し変化。中村に代わり河井を起用。ビルドアップの時に河井を CBの左に降ろしてプレーさせている。
後ろ3枚の清水。そして左は組み立ての起点になれる河井。河井がボールを持って前をのぞくとC大阪はSHの坂元を前に出してプレスにくる。坂元が前に出るのでC大阪の右SB松田はカルリーニョスと片山を気にする状態。これで松田を狙い打つように長いボールを左奥に送ってサイドの起点を作っていた。
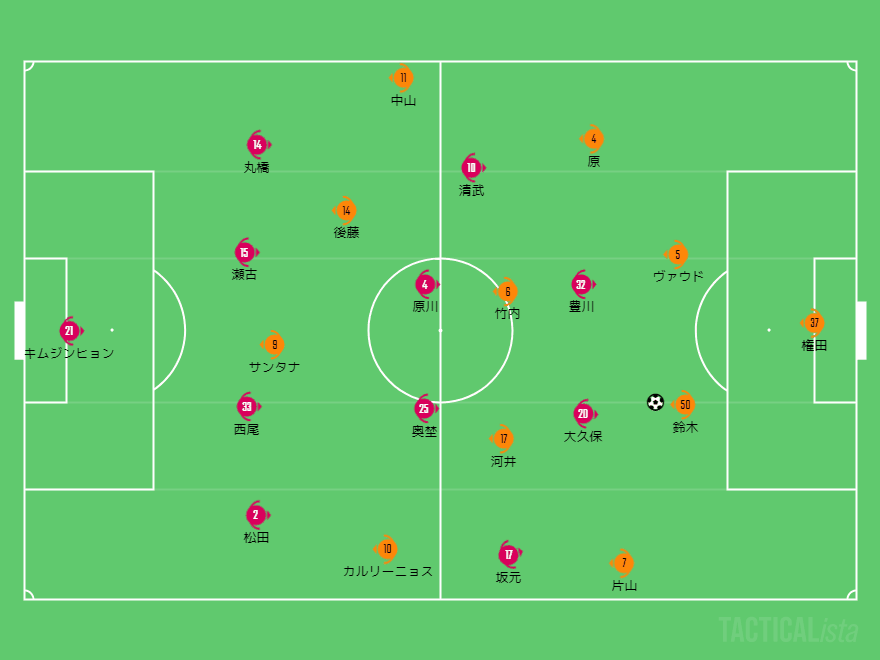
このビルドアップから何度かチャンスが生まれている。
またC大阪のCBは割とボールサイドにスライドしてくるが、逆サイドのSBやSHはあまり絞ってこない。そのため右サイドから後藤や中山がゴール間に入ってくると浮きやすくなっていた。例えば開始直後の中山、また10分の後藤の決定機。これらの場面で彼らはほぼフリーでシュートを撃てている。
しかし前半の半ば頃から坂元がやや後ろやサイドのスペースを気にするようになる。さらにそれまでDFラインにとどまる意識が見えた松田がサイドに早めに出てくるようになった。これでC大阪の守備対応が明確になったように感じる。よって清水は徐々に左サイドで良い状態でボールが持てなくなってしまった。
一方、右サイドに目をうつす。右サイドのざっくりした役割はSHの中山は幅取り役、IHの後藤はセカンドストライカー。なので後ろの組み立てはCBのヴァウドとSB原で行いたい。しかしヴァウドがオープンな状態でボールを持てないため相手の守備を動かせない。ときおり後藤が降りてボールを受けるものの右の組み立ては原が大きなウェイトを担う状態になっている。
原はポジションを中や外に動いて中山へのコースを作ろうとしていたが、清武は原のポジションに動かされず基本はサイドをケア。原は単独で打開するタイプでないため相手に対応されるとよい状態で中山にボールを届ける場面は少なくなってしまった。
次に守備の局面を見ていく。
システムでいうと4-4-2と4-5-1の中間のよう。しかしシステム表記に無理に当てはめるのはあまり意味がないと思える。ラインを作ってブロックを固めるより、ボールと味方の位置を見ながらポジションを取っているように見えるからだ。具体的にみていく。
まず相手が後方で持つ時はサンタナと後藤でプレスに行く。ただし奪いにいくよりサイドを限定するようなプレスだ。
そしてFWの脇に運ばれたらサンタナがサイドを限定したまま後藤が少し斜めに下がる。これで斜めに中へ入れるコースを消す。(下図)
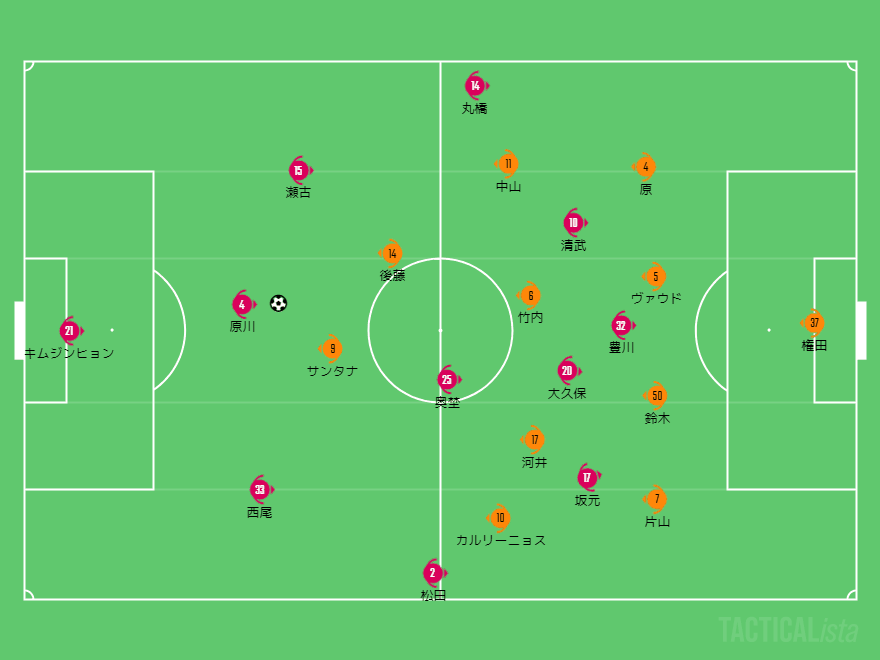
次に左に運ばれた時。先ほどと同様にサンタナが下がる時もあるが、河井やカルリーニョスが出る時が多い。その時の動きを下図に示す。
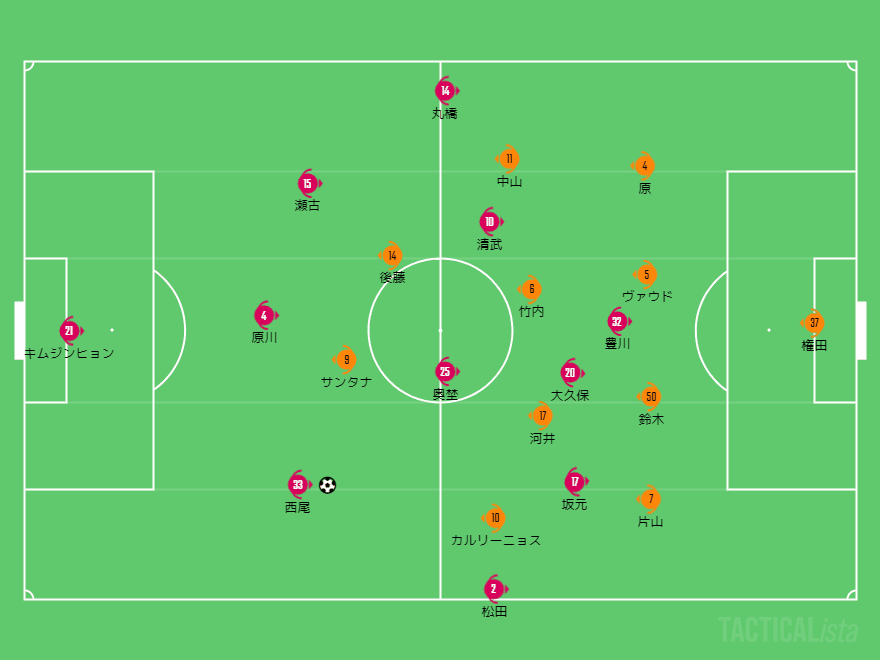
例えばカルリーニョスが前に出たら河井と竹内はスライド。カルリーニョスはサイドを切りながら前に出るが、それでも通されたら河井がさらにサイドにスライドする。そしてカルリーニョスは河井のいたスペースに入る。こうして常に中を埋めながらサイドで奪う。
その際、逆側のスペースが気になる場合は後藤が下がって中盤ラインを形成する。これで見た目は4-5-1。
当然必ずこの通りに動くわけではなく、ボールと味方の位置によってプレスとスペースを埋める選手は変化する。
この試合でも相手が縦パスを入れるコースを消せており、セットした時はほぼ崩されることはなかった。
しかし少し気になることが2つ。あくまで気になる程度。
1つはサイドチェンジをされた時。しかもこちらの2列目を越えるように斜めに深くサイドチェンジされた時だ。

上図のようなボールを入れられると、右サイドで前向きな守備から、左側にスライドしながら後ろに下がる守備に変化する。つまり身体の向きと動きの方向を逆に変えなければならない。しかも移動距離が長いため即座にポジションを取れない。
C大阪はサイドチェンジから清水がセットしきる前にサイドから真横にパスを入れていた。
守備をセットできないと個々の守備対応の強さに左右される。C大阪のチャンスはこのパターンが多かったように見えた。
もう一つ気にになったのが相手のボールを奪っても、再びすぐ奪われてしまった時だ。切り替えの切り替え。これは福岡戦で特に目についた。攻撃に転じる際にIHが前に上がっていくためどうしてもアンカーの竹内の周辺にスペースができてしまう。福岡は意図的にそこを狙っていた節も感じられた。ここを狙われた時にどう修正するかは注目だ。
選手をあまり前に上げず後ろで作り直すのか。または中盤にボールをガードしながらキープできる選手を起用するのか。セレッソ戦では中村の代わりに河井を起用し保持時に低い位置に置いたのはここも関係しているのだろうか。そこはわからない。今後の起用を見ながらまた考察を進めていきたい。